1都3県 投資用マンションのDATAによる分析
投資用マンションは1都3県に4,900件弱あり、シェアは1割に達しています。「投資用マンション」という用語にとくに定義はないので、ここでは「平均面積30㎡以下」を対象にしました。
そのメリットは少ない自己資金で不動産投資ができること、銀行金利以上の表面利回りが期待できること。昨今の低金利状況のなか資産運用物件として注目されています。そして賃料収入の期待が購入の背景になることから、立地面では利便性の高い市街地にあり、しかも最寄り駅から徒歩で数分以内というのが主流です。
まずその形状から見ていきましょう。ワンルームタイプの居室が主になることから、建物は規模・階高の数値から想定される外観よりは小さく感じます。建物の規模は30戸以下が37%、31~60戸が44%、市街地中心に立地していることから大型タイプは稀です。階高は5階建以下が4割弱、6~10階建が4割強という構成です。
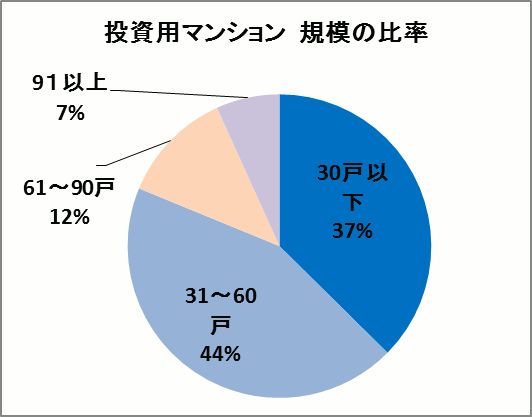
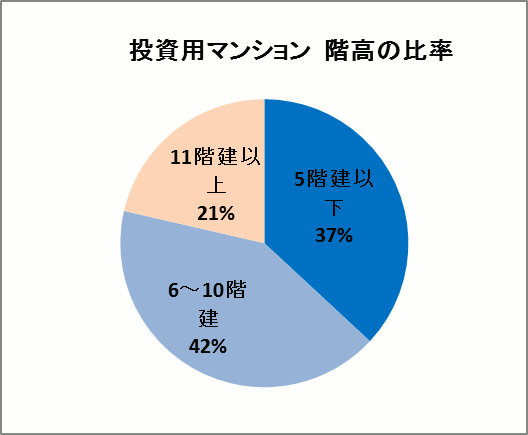
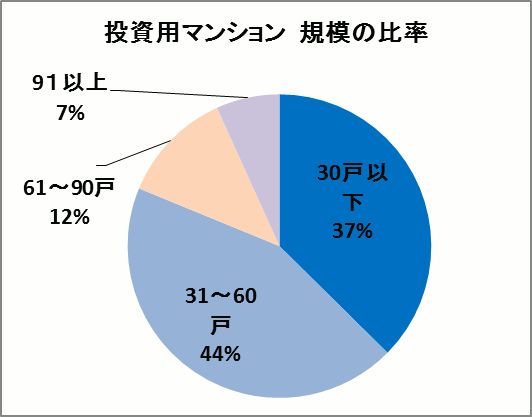
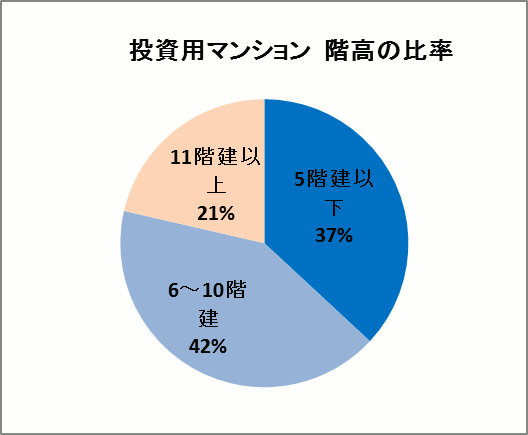
1都3県におけるシェアは東京都が8割を占め、まさに一極集中の構図です。そして都心部に近いほど集中度は高くなります。都内の区別ストック数では、新宿区が382件で抜けており、港、世田谷、杉並、大田、渋谷、文京、豊島、中央の各区が200件を超えています。区ごとのシェアでは、千代田、中央、新宿の3区が2割強を占め、文京、豊島の両区がこれに続いています。

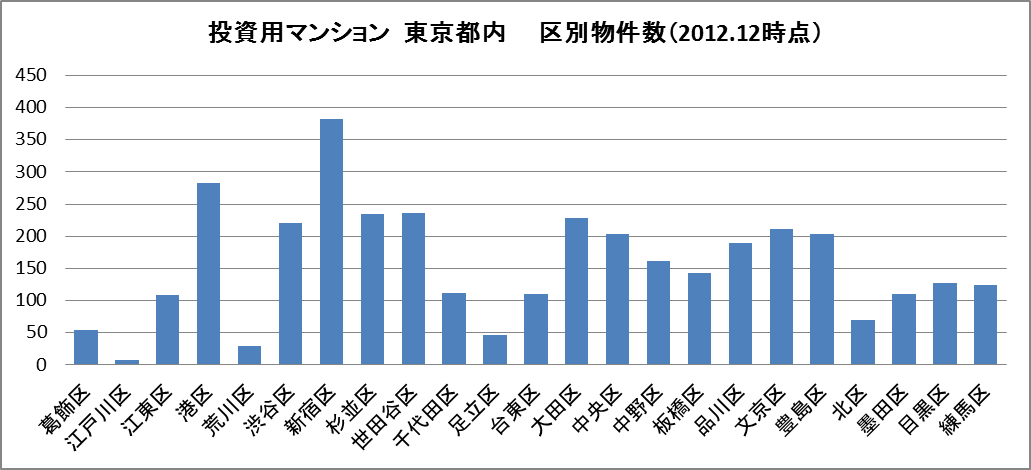
では投資用マンション数が一番多い新宿区の状況をくわしく見てみましょう。下のグラフは最近10年間の「竣工推移」と「価格推移」です。
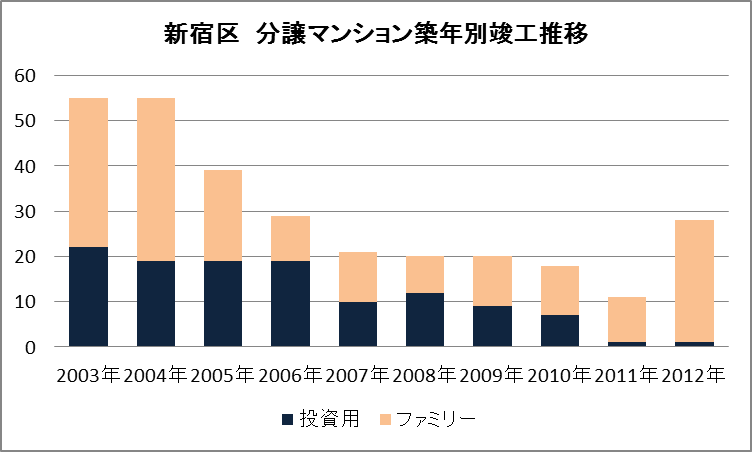
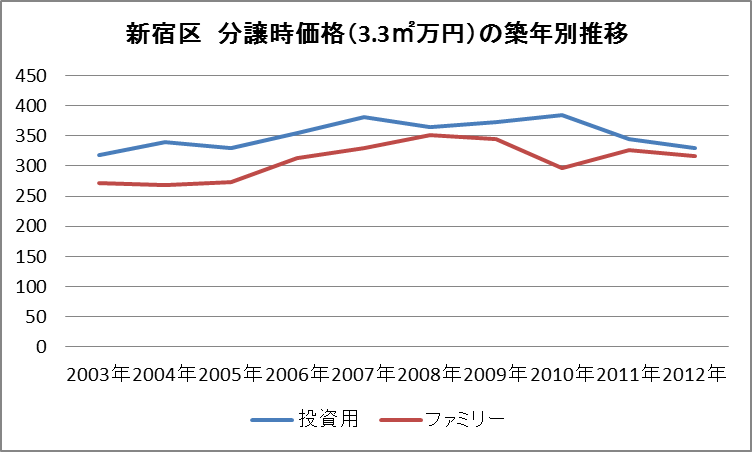
まず新宿区全体の竣工推移をみると、2004年から2011年までは右下がりです。これは1都3県の推移に似ていますが、「ファミリー用」(平均面積31㎡以上)と「投資用」に対比してその推移を見ると不可解な現象が見えてきます。
その事例としてピークの2004年と底に近い2008年の竣工数を比較してみましょう。区全体では64%の減です。その内訳をみると「ファミリー用」が78%の減に対し、「投資用」は36%の減。そして「ファミリー用」と「投資用」の比率は65:35から40:60に逆転、「投資用」のシェアが60%と異常に高くなっています。
さらに2011年、2012になると状況は一変、「ファミリー用」が持ち直し「投資用」が激減します。その結果、対比は96:4%となり再逆転します。この起伏の激しい推移を局地的な異変とみるか、それとも先行きへの懸念の兆しとみるかという課題が残ります。
分譲時価格(3.3㎡単価)の推移を見ましょう。通常、「投資用」の方が「ファミリー用」より15~20%程度高く設定されています。新宿区においても同様に推移していますが、詳しく見ると価格の上下動と竣工数の動向にズレがあります。まず「ファミリー用」の価格は2006年から2009年まで上昇し、この間の竣工数は減少しています。一方「投資用」は2010年以降価格が下落、竣工数も減少しています。価格が上がれば、購入意欲が減退し、竣工数も減るのが一般的なパターンですが、「投資用」にみられる双方右下がり現象は先行きに不安を感じます。
投資用マンションというと新しいものに感じますが、「平均面積30㎡以下」のマンションという対象で見ると、1974年ごろから存在しています。その40年間の竣工推移を見てみましょう。
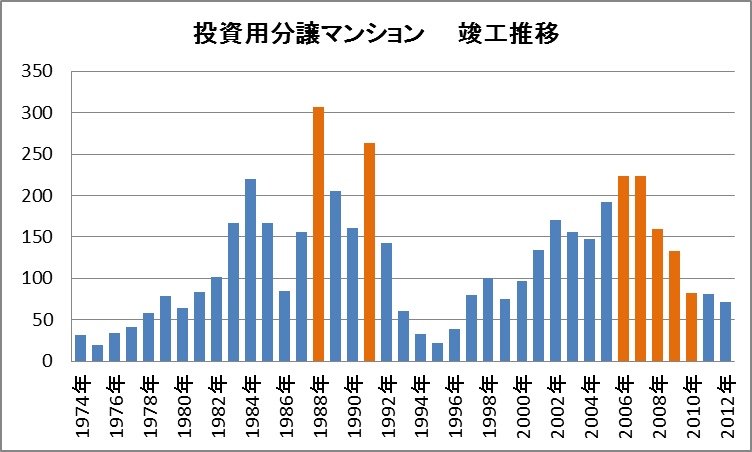
グラフが示すようにバブル崩壊後の1994、1995年を底にして前後に二つの山がみられます。ここでは便宜上、底の時期を境に前期および後期に分けて分析します。
この時期はいわゆるバブル経済がピークに向い、都心では超高額物件、投資用のワンルームマンションがブームになり、一次取得者向けのファミリーマンションは郊外へ押し出されるという状況でした。
ブームの頂点はバブル期、値上がり益を期待しての購入が増え1988年には竣工数308件、シェアは24%に達しています。分譲主はスカイコート、ダーウィン、杉山商事、ニッティライフなどの専門会社と分譲会社大手の大京、コスモスイニシアが競っています。
この期に入るとファミリーマンションの竣工数は右下がりになり、2010年を境に持ち直しの傾向を見せています。内閣府による首都圏における人口の社会増は、この年帯に入って0.7~0.15と落ち込んでいることが影響したのかもしれません。
一方、投資向きマンションは2007年のピークまで右肩上がりに推移し、2006年から2010年の5年間は竣工数の減少はあるがシェアは18~20%を維持し、ファミリー用の落ち込みを支えるほどの堅調振りです。
分譲時のPRにおいても「投資向きであること」を全面に出し、表面利回りを明示した新たな手法取り入れるなどの工夫がみられます。分譲主はエフジェーネクスト、TFDコーポレーション、ト―シンパートナーズ、日商はハーモニが加わり競っています。
ところが一転、最近の3年間、2010年~2012年の推移をみると「ファミリー向」が超高層マンションの竣工や高級化志向の取り入れによって持ち直しているのに対し、「投資向」は停滞気味です。前項での新宿区の状況が局地的な異変ではなく、何らかの兆しであるのかも知れません。こうした先行きの道筋が見えない状況について専門筋はつぎのようにみています。
- 事業主の寡占化が進行し、供給の広がりがみられないこと。
- 購入主体であるサラリーマン世帯の所得が落ち込んでいること。
- 入居する20~30歳代に不況の影響がおよび借り手が付くかの不安があること
上記の3点を挙げています。 2013年前期の竣工状況からも回復の兆しは見当たりません。